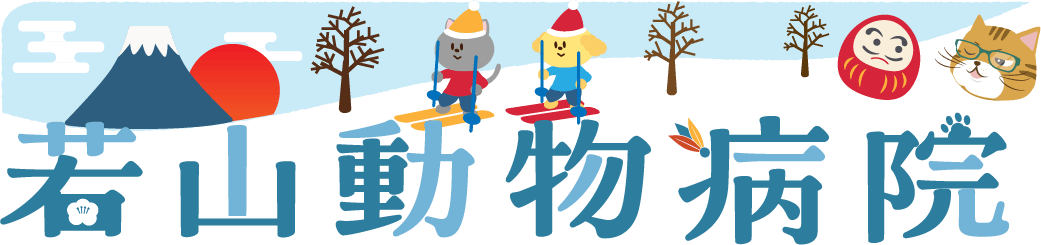若山動物病院ブログ
新しいものが苦手

猫は、よく「偏食家」「神経質」などと言われることがありますよね。
そのような猫の性格の背景には「ネオフォビア」という行動特性が深く関わっています。
ネオフォビアとは「新しいものに対する恐怖や警戒心」のことです。
これは猫に限らず多くの動物に見られる本能的な防衛行動なんですが、特に猫ではその傾向が強〜く現れます。
ネオフォビアってなに?
ネオフォビアは直訳すると「新奇恐怖症」と言います。
ヒトでも新しい環境や初対面のヒトに対して緊張したり、慎重になることがありますよね?
それと同じなんですが、猫ではこの傾向がとても強く、しかも行動にもハッキリと現れます。
たとえば次のような場面でネオフォビアが、よく見られます。
- 食べ慣れたフード以外は口にしない
- 新しいおもちゃや家具に近づかない
- 引っ越しや模様替えなど生活環境の変化で食欲が落ちる
- 来客や新しい同居動物を怖がり避ける

いやぁ〜猫は「わがまま」だし「臆病」だから、こうした行動をとっちゃううんだよね!

「臆病」じゃなく「用心深い」んだよ!
それに、それらの行動は「知らない=危険かもしれない」という生存本能からくる当然の反応なんです!
なぜ猫はネオフォビアになりやすいのか?
猫は自然界では単独で狩りをし、テリトリー内で生活する生き物です。
そのため新しいものに興味を持って近づくより、警戒して避ける方が生存確率が高かったのです。
このように進化の過程で、ネオフォビアの傾向が強まったと考えられています。
特に成猫になるとその傾向が強くなり、若い頃に経験したもの以外にはなかなか慣れようとしません。
これがフードの切り替えが難しくなってしまう理由の一つになっています。

「単独行動ってことは、自分の身は自分で守るってこと」
だから用心深くなったんだよ!
そこが犬との違いだよね!
食べ物に対するネオフォビア
猫の偏食の多くは、この「食べ物に対するネオフォビア」によるものとされています。
典型的な行動には以下のようなものがあります。
- 新しいフードはニオイを嗅ぐだけで口にしない
- フードの粒の形状が違うだけで食べようとしない
- 一度嫌な思いをしたフードを二度と食べない
ただ猫は「ネオフィリア(新しいものが好き)」な一面も併せ持っています。
そのため「ネオフォビア」には、個体差があります。

新しい物には興味津々なんだけどさ・・・
それでもニオイや音には、とっても慎重になってしまうんだよね。
ネオフォビアへの上手な対応方法
ネオフォビアとうまく付き合うには、「無理に慣れさせようとしないこと」が第一です。
以下のような工夫が役立ちます。
子猫期(生後2~3ヶ月)
多数の経験を積ませる
さまざまな音・ニオイ・人・食べ物に慣れさせることで、成猫になってからのネオフォビア傾向を軽くすることができます。
新しいものは少しずつ慣らす
新しいフードは従来のフードに混ぜ、徐々に割合を増やしていくのが基本です。器や環境の変化も、猫の様子を見ながら段階的に進めましょう。
新しいものをポジティブな体験と結びつける
例えば新しいおもちゃで遊んだあとに好物のおやつを与えるなど、「新しい=楽しい」と学習させると受け入れやすくなります。
飼い主が安心感を与える存在になる
信頼する飼い主がそばにいると、猫も安心して新しいものにチャレンジできるようになります。
焦らず見守る
猫のペースで慣れるのを待つことも大切です。
無理強いはかえって警戒心を強めてしまいます。
まとめ
ネオフォビアは、猫にとってごく自然で正常な本能のひとつです。
特に成猫になると「新しいものを拒否する」こと自体が危険を避けるための手段でもありました。
そのため無理に矯正するのではなく、その性質を理解しながら付き合うことが大切です。
「またこの子、いつものフードしか食べない・・・」
それは「生き延びるための知恵」が働いている証拠、なのかもしれませんよネ!