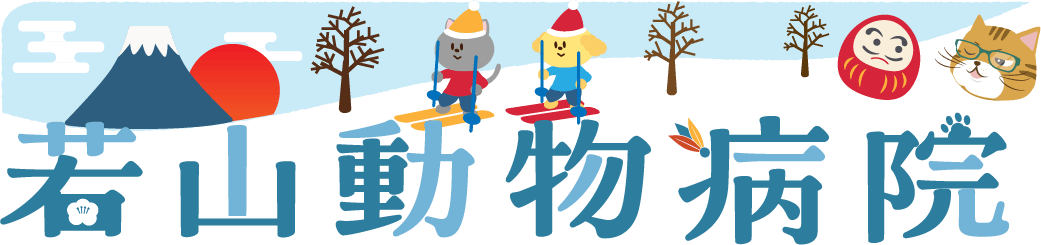若山動物病院ブログ
猫の「マルチモビディティ」を知っていますか?

「この頃、よくお水を飲むし、トイレの回数も増えた気がする…」
「なんだか最近、よく鳴くし、夜にウロウロして落ち着かない」
そんな猫ちゃんの変化に気づいたことはありませんか?
猫がシニア期(だいたい7~10歳以上)を迎えると、ひとつの病気ではなく複数の病気を同時に抱えることがあります。
この状態を医学用語で「マルチモビディティ(多病併存)」と呼びます。
今回は、このあまり聞き慣れないけれどとても重要な概念についてです。
マルチモビディティとは?
マルチモビディティ(Multimorbidity)とは、2つ以上の慢性的な病気が同時に存在している状態を指します。
ヒトの高齢者医療ではよく使われる言葉ですが、猫ちゃんにも無関係ではありません。
例えば、こんな組み合わせがよく見られます。
- 慢性腎臓病(CKD)×高血圧
- 甲状腺機能亢進症 × 心疾患
- 糖尿病 × 歯周病
- 認知機能不全(猫の認知症)×関節炎
これらの病気は、それぞれが猫の健康に影響を与えるだけではありません。
それぞれの病気が、お互いに悪影響を及ぼし合うことが多いんです!
なぜシニア猫に多いの?
加齢に伴って、猫の体のさまざまな臓器や機能が少しずつ衰えていきます。
これにより、複数の病気が重なって発症するリスクが高まるのです。
また、猫は「我慢強く、症状を隠す動物」です。
1つの病気だけでも気づきにくいのに、複数の病気が進行して初めて異変に気づくこともあります。
気づきのヒントは「いつもと違う」サイン
マルチモビディティの猫ちゃんには、以下のような複合的な症状が見られることがあります:
食欲があるのに体重が減る(甲状腺疾患?腎臓病?)
水をたくさん飲むが元気がない(糖尿病?腎不全?)
夜中に鳴く・ウロウロする(認知機能不全?高血圧?)
口臭が強い、元気がない(歯周病?便秘?)
「何が原因かわからない」という複雑な症状の裏に、複数の病気が隠れている可能性があるのです。
ケアの工夫と注意点
マルチモビディティの猫ちゃんには、次のような配慮が大切です:
定期的な健診
血液検査、尿検査、血圧測定などを組み合わせて、見えない病気を早期に見つけ出します。
症状の記録
食欲・飲水量・排尿・行動の変化など、日々の観察メモが診断のヒントになります。
薬の飲み合わせに注意
複数の薬を飲む場合、副作用や相互作用のチェックが必要です。
生活環境の見直し
トイレの数を増やす、段差を減らす、寝床を温かくするなど、生活の質(QOL)を保つ工夫をがします。
飼い主さんへメッセージ
「高齢だから、もう仕方ない」と思ってしまうかもしれません。
でも!
複数の病気とうまく付き合いながら、穏やかな毎日を送ることは可能です。
病気の完治ではなく、快適に暮らすことを目標にしてあげることが大切です。
そのためにもマルチモビディティを正しく理解することが、シニア期の猫ちゃんと心地よく寄り添う第一歩になります。