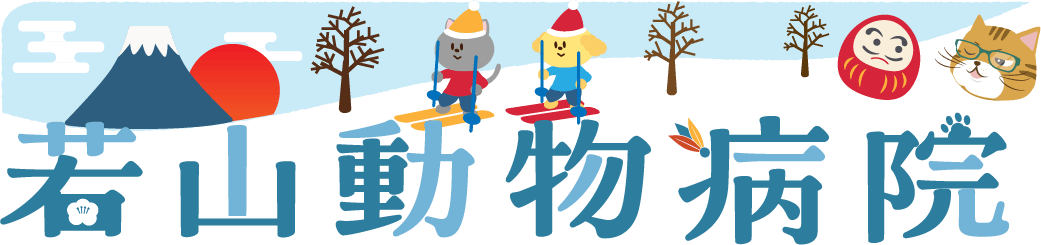若山動物病院ブログ
癲癇みたいな発作

「うちの犬が突然バタバタして、まるで癲癇(てんかん)のような発作を起こしたんです・・・」
そんな来院が、時たまあります。
発作と聞くと「脳の病気?」と思われがちですが、原因は必ずしも脳にあるとは限りません。
今回ご紹介するのは腎臓のトラブルによって高BUN(尿素窒素)が起き、それが発作の引き金になったケースです。
発作=必ずしも癲癇ではない
犬の「発作」には大きく2つのパターンがあります。
本当の癲癇発作
脳の神経細胞が異常に興奮し、けいれんや意識を失うこともあります。
癲癇に似た症状(二次的な発作)
低血糖・肝不全・腎不全・中毒など、カラダの臓器トラブルが原因で脳に影響が及び、発作みたいな症状を見せる。

今回のテンカンみたいな発作、つまり「見た目はテンカンでも、原因は腎臓」だったってことでした。
BUNとは?
BUNとは、血中能祖窒素=Blood Urea Nitrogenの略です。
血液の中に含まれる、たんぱく質が分解されたときにできる老廃物の量を示す指標になります。
どうやってできるの?
1. 食事から摂った たんぱく質 が体内で使われる
2. その過程で アンモニア という毒素が発生する
3. 肝臓がアンモニアを「尿素」に変える(無毒化)
4. 腎臓が尿として排泄する

つまり 肝臓で作られ、腎臓から排泄される老廃物 が「尿素」なんです。
その尿素に含まれる「窒素成分」の量を測ったものが「BUN」です。
正常値(犬の場合)
検査機器によって多少のズレはありますが、おおよそ 10~30 mg/dL の範囲です。
それ以上になると「高BUN」=尿素が血液に溜まっている状態となります。
BUNが高くなる原因
・腎不全(老廃物を排泄できない)
・脱水(血液が濃縮されて数値が高くなる)
・たんぱく質の多いものを食べた
・胃腸などの消化管からの出血(出血した血液中のたんぱく質を腸で分解されると尿素が増える)
BUNの意味
腎臓の働きをチェックする指標として使われます。
しかし「肝臓や胃腸などの消化管、食事の内容など」にも影響されてしまうため、他の検査と併せて行います。

腎臓の検査では、必ず クレアチニンやSDMA などの他の検査と併せて行うんだよ!
また腎臓から蛋白がオシッコに漏れてないかを検査することもあります!
高BUNで起こる症状
BUNが高くなると、犬の体にはこんな変化が現れます。
・食欲が落ちる、吐き気や下痢
・元気が無くなったり無気力に
・口臭(アンモニア臭)がする
・ふらつきや運動失調
・そして「ケイレンや発作」

腎不全の状態が進むと脳に毒素が回り、「癲癇のように見える症状」を起こしてしまうのです。
飼い主さんが注意すべきポイント
「発作=癲癇」と思い込まず、次のことに注意しましょう。
1.発作が起きたら病院へ
たとえ短時間でも発作を繰り返す場合には、良いことはありません。
2.血液検査を受ける
発作の原因を探るには脳だけでなく、血液検査で腎臓・肝臓・血糖値などを確認する必要があります。
3.慢性腎臓病のサインを見逃さない
・水をよく飲む
・おしっこの量が多い
・体重が減る
こうした症状の場合には、早期の腎臓のトラブルの合図ってこともあります!
まとめ
犬の痙攣した発作といえば癲癇を疑いがちですが、実際には他にも原因がある場合もあります。
例えば今回のように、腎臓病(高BUN)による尿毒症が原因のケースです。
そのため「症状だけで決めつけないこと」が大切です。
もし突然に発作を起こしたら、慌てずに相談してください。