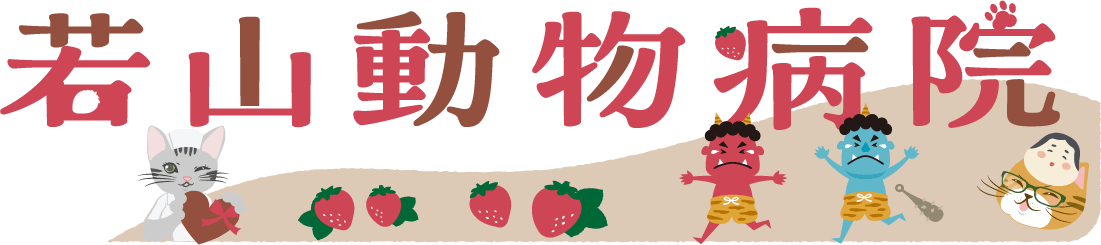若山動物病院ブログ
かくれ脱水を知っていますか?

冬こそ気をつけたい「見えない脱水」
今「いぬのきもち・2026年2月号」の記事の手伝いを行なっています。
今回は第2特集の「冬の”かくれ脱水”を防ぐ・飲水量チェック(仮)」という企画です。
なぜ水を飲むことが大切なの?
犬のカラダの60~70%は、水でできています。
この「水」は、血液の流れや体温調節、老廃物の排出、消化、代謝など生命活動のもとなんです!。
たとえ少しでも足りなくなるとカラダのバランスが崩れ、内臓や皮膚の働きが鈍くなってしまいます。
冬こそ注意したい理由
冬は意外にも脱水が起きやすい季節なんです。
その理由は、以下のようになります。
- 乾燥した空気:暖房を使うと湿度が下がり、皮膚や粘膜から水分が蒸発しやすくなります。
- 水をあまり飲まない:寒さのせいで喉の渇きを感じにくくなり、自然と飲む量が減ります。
- 免疫力の低下:粘膜が乾くとウイルスや細菌が入りやすくなります。
- 皮膚や被毛のトラブル:水分不足でフケやかゆみ、乾燥性皮膚炎が起こりやすくなります。
つまり・・・
ちゃんと水を飲むことは、健康を守る大切な「ケア」の一つなんですよ。
「かくれ脱水」ってなに?
「かくれ脱水」とは、カラダの中では水分が足りていないのに、外から見ても分かりにくい状態のことです。
元気そうに見えても、実は体の中ではジワジワと水分不足が進んでいる場合があります。
冬に多い理由
- 寒くて水を飲む量が減る
- 暖房で空気が乾燥している
- 飼い主さんも「脱水」を意識しにくい
寒くなると、あまり気にならないような小さなことが重なってくるんです。
そして気づかないうちに「かくれ脱水」となり、しかもが進んでしまうのです。
かくれ脱水になるとどうなるの?
水分が足りない状態が続くと、カラダの中では様々なトラブルが起きてしまいます。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 腎臓に負担 | 血液がドロドロになり、腎臓の働きが低下。尿石や腎不全のリスクも。 |
| 便秘 | 便の水分が減り、硬くなって排出しづらくなる。 |
| 皮膚のトラブル | フケ・かゆみ・毛ヅヤの悪化など。 |
| 血流・代謝の低下 | 血の巡りが悪くなり、体温が下がりやすくなる。 シニア犬では心臓病の悪化要因にも。 |
見た目にはわからなくても、カラダの中じゃ「SOS」が出ているんですよ!
かくれ脱水に気づくサイン
「なんとなく元気がないな…」
そんな時は、次のような変化をチェックしてみてください。
- オシッコの色が濃い、量が少ない
- 皮膚をつまむと戻りが遅い
- 毛ヅヤが悪く、皮膚がカサカサ
- 鼻や肉球が乾いている
- 便が硬い、コロコロしている
- 食欲が落ちた、なんとなくだるそう
こうした小さなサインを見逃さないことが大切です。
冬にかくれ脱水になりやすい犬
| タイプ | 理由 |
|---|---|
| シニア犬 | 腎臓の機能が落ち、水分を保ちにくい |
| 超小型犬 | 体が小さく、少しの水分変化でも影響を受けやすい |
| 寒がりな犬 | 冷たい水を嫌がる |
| 運動不足の犬 | のどが乾かず、水を飲むきっかけが少ない |
| 持病のある犬 | 利尿剤などで水分が失われやすい |
| 術後・療養中の犬 | 食欲や元気が落ち、自然と飲水量が減る |
「水の飲ませすぎ」は大丈夫?
健康な犬であれば、多少多めに水を飲んでも問題はありません。
カラダは必要のない水分をオシッコとして、カラダの外に排出します。
むしろ「飲ませすぎ」よりも「飲ませなさすぎ」の方が、ず〜っと危険です。
ただ心臓病や腎臓病、糖尿病などの病気がある場合は、注意が必要ですよ。
それは病状によっては、水分量の制限や管理が必要な場合があるからです。
何か気になることがある場合には、獣医師に相談してくださいね!
どのくらいの水を飲めばいいの?
目安は、1日あたり体重1kgあたり40~60mLです。
たとえば体重5kgの犬なら、1日で約200~300mLが目安となります。
ただ食べてるフードの種類によっても、違いがあります。
- ドライフード中心の場合 ▶️ 水を多めに必要とする
- ウェットフード中心の場合 ▶️ フードからも水分が摂れる

「冬は飲む水の量が減りやすい」と言われますもんね!
そのため、いつもより少し多めにお水を意識して用意しておくことにしまぁ〜す!
水分量を簡単にチェックする方法
① 朝、飲水用の器に水を入れる
② 計量カップに決まった量の水を入れておく
③ 飲んで減った水の分を計量カップから足す
④ 飲んだ水の量を測る
計量カップに残った水の量を朝入れた量から引く
フード中の水分(ウェットフードなど)も加算
これで1日に飲んだ水の総量が簡単にわかります!
冬に飲水量を増やす工夫
| 方法 | 内容・ポイント | 特におすすめ |
|---|---|---|
| 朝いちばんに白湯を! | 人肌(犬肌?)程度(35〜40℃)に温めると飲みやすい | シニア犬・寒がり犬 |
| 香りをつける | ササミの茹でた湯や、無塩の煮干し水を少し加える | 食欲が落ちた犬 |
| ごはんにお湯をプラス | ドライフードを「おじや風」に・・・ | 歯が弱い犬 |
| 水ゼリーを利用 | 遊び感覚で水をとる | 若い犬・遊び好きな犬 |
| 器の高さを調整 | 飲みやすく首の負担も減る | シニア・小型犬 |
| 加湿器を使う | 室内湿度40〜60%を保つ | 乾燥肌の犬 |
| 軽い運動 | 遊びや散歩で自然に喉が乾く | 室内犬全般 |
| 防寒対策 | 服や腹巻きで冷えを防ぐ | 寒がり・高齢犬 |
飼い主さんへのメッセージ
水を飲むことは「一番シンプルで確実な健康ケア」です。
冬は脱水しやすい季節です。
オシッコの色や便の硬さ、皮膚の乾燥などに注目してくださいね。
水を飲むのことは習慣ですので、チョットした工夫で「自然に飲みたくなる」環境を作ってあげましょう。
たっぷりの水は、腎臓・皮膚・免疫・代謝すべてを守ります。