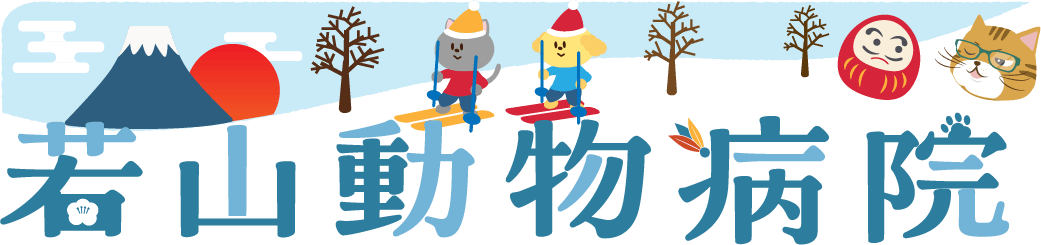若山動物病院ブログ
脳が正常に働くためには
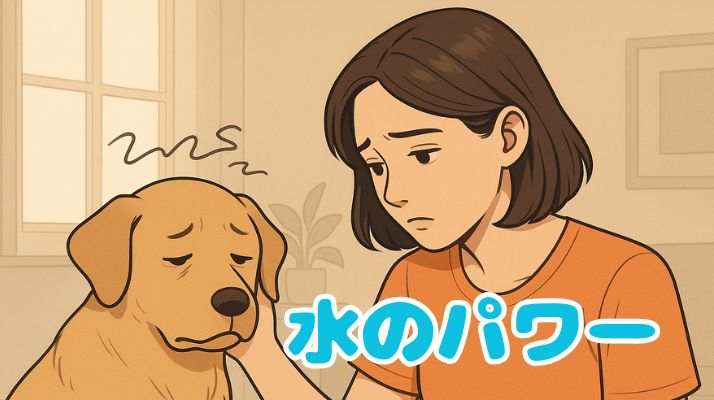
ヒトも犬も猫も、その体の約60~70%は水でできています。
そして水は単なる「飲み物」ではなく、「生命を動かす燃料」のような存在なのです。

脳の働きに欠かせないのが「グルコース(ブドウ糖)」や「酸素」、そして「水」です。
では、脳にとって「水」はどんな働きをするのでしょうか?
脳の60%は水でできている
脳はカラダの中で、最もエネルギーを使う臓器なんです。
そしてヒトの場合では、脳の約80%が水分なんです。
そのため、わずかな水分の変化でも脳の働きが鈍くなります。
例えば・・・
カラダの水分が1~2%失われただけで集中力が落ち、3~4%減ると頭痛やめまいが起こると言われています。
犬猫でも同じで、軽い脱水でも「元気がない」「反応が鈍い」「歩き方がふらつく」などの変化が現れます。

それって・・・
脳の神経細胞が水分不足によって、うまく働けなくなることからの症状ってことなのね?
脱水って、怖いわね!
「情報伝達」に欠かせない水の役割
脳の中では、無数の神経細胞が電気信号を使って情報をやり取りしています。
この信号をスムーズに伝えるために必要なのが「水分バランス」です。
水は、神経の周りを取り囲む脳脊髄液の主成分でもあります。
脳脊髄液はクッションのように脳を守り、老廃物を運び出す働きもしています。

もし水分が不足すれば、脳脊髄液の流れが悪くなり脳の中の老廃物が溜まってしまうってことなのね。
「酸素」や「栄養」を運ぶのも水の仕事
血液や体液は、ほぼ水から作られています。
つまり水は脳のエネルギー源であるグルコースや酸素を、脳へ届ける運び屋の働きをしています。
この働きが悪くなると、脳はエネルギー不足に陥ってしまいます。
また血液がドロドロになると流れが悪くなり、脳が酸欠状態にもなってしまいます。
それは犬や猫でも同じで、血液の流れが悪くなると意識がもうろうとしたり、反応が遅くなったりします。

「脳を元気に保つ」には「カラダの水分を保つ」ってことなのね。
水は「脳の冷却装置」でもある
脳は常に活動しているため、熱を生み出します。
その熱をうまく逃がしてくれるのも、水の力です。
そのため水分が不足すると、熱が逃げずに熱中症や脳の過熱が起こりやすくなります。
特に犬や猫は体温調節が苦手なため、脱水状態になると命に関わる危険があります。
「のどが渇いた」と感じた時点で遅い!
実は「のどの渇き」を感じた時点では、すでにカラダは1~2%の水分を失っていると言われています。
つまり、軽〜い脱水状態になっているってことなのです。
脳はとても敏感な組織です。
そのため、この段階で「ボーッとする」「集中できない」「反応が鈍い」などの変化が出てきます。
犬や猫は自分で「のどが渇いた」と言えません。
そのため、飼い主さんが飲水量の変化を観察してあげることが大切です。
- 水を飲む回数が減った
- 水の減りが遅い
- オシッコが濃い・回数が減った

もしこのような変化があれば、早めに受診を考えて下さいね!
脳を守る「水分ケア」のポイント
1. いつでも新鮮な水を
汚れた水は飲まなくなる傾向にある子が多くいます。
そのため、1日に数回は水の入れ替えをしてあげた方が良いことも!
2. 水の温度も大切
冷たすぎず、室温程度が最も飲みやすい温度とも言われています。
ただ中には冷たい水の方が好きな子もいますので、水の好みの温度を調べてあげましょう。
3. 飲みやすい器を
浅めの器や循環式給水器は、猫にも人気です。
また好きな器があれば、飲む量が増えることがあります。
4. 水分をフードからも
ウェットフードやスープなどからも、水分は摂れます。
5. シニア期こそ意識を
老齢になると「のどの渇きの感覚が鈍る」ため、水分補給のサポートしてあげましょう。
まとめ
グルコース(エネルギー)や酸素(燃焼源)があっても、それを運ぶ「水」がなければ、脳は働けません。
水は脳にとり必要不可欠なもので、以下のような様々な働きをしています。
- 情報伝達を助け
- 老廃物を流し
- 体温を調整し
- 血流を支える
ヒトも犬も猫も、健康な脳を守るためには「水」の飲む量には注意しましょう!
そして今日から「水は脳が喜ぶモノ」と意識して下さいね!