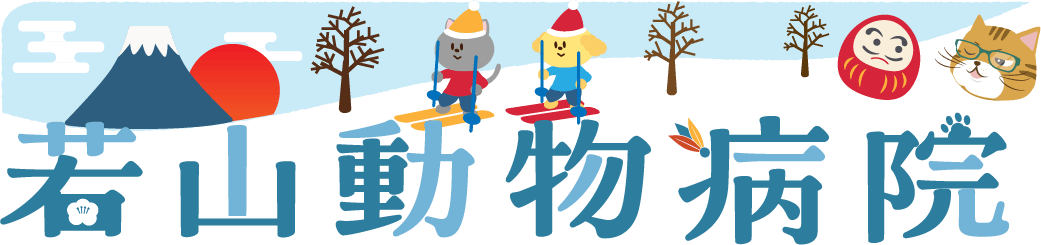若山動物病院ブログ
歯肉の腫れから

今年の1月、あるワンちゃんの「歯肉に小さい腫れ」が見つかりました。
歯周病からの歯肉の腫れとは、様子が違う・・・
そのようなことから、晴れた組織の一部を取って検査をしたところ・・・
診断は「口腔内骨肉腫」、それは顎の骨にできた悪性腫瘍でした。
それまでは、この子はチョットわがままな性格だったんです。
ごはんにもあまり興味を示さず、食べても好き嫌いが激しく・・・
だから、食べさせるのにひと苦労する日々が続いていました。
ところが不思議なことに腫瘍が見つかり治療を始めてからは、まるで別の犬のように変わったのです。
選んだ治療方法は
口腔内骨肉腫の第一選択は外科手術です。
今回の場合には上顎の腫瘍のできてしまった部分を切り取ってしまう、そのような手術になってしまいます。
ただ完全に切除することが難しいし、顔の形も変わってしまいます。
それだけでなく、上顎を取ってしまたら食べるのも大変になってしまいます。
そのため飼い主さんも、手術は同意が得られません。
また放射線治療や抗がん剤も同様に、同意が得られません。
そこで代替療法として「高濃度ビタミンC療法’を、先月からは「生活の質改善」を目的として免疫療法である「活性化リンパ球療法」が行われました。
また腫瘍が見つかった時から、緩和ケアも始めました。
まずは「栄養サポート」です。
腫瘍が出来てしまうと徐々に痩せ、最終的には腫瘍に負けてしまいます。
そのような状態になるのを遅らせるために、とにかく食べて運動して筋肉をつけることをしたのです。
そして「口腔ケア」です!
歯周病は万病の元ともなり、今回は口の中の腫瘍であるため口腔内の衛生管理には十分に注意しました。
「がんとともに過ごす時間を快適にする」工夫も行っています。
痛みが出てきたら疼痛管理も行う予定ですが、現在は食欲もバリバリで痛みは無さそうです!
治療とともに変わった性格
選んだ治療である高濃度ビタミンC療法は、ビタミンCの持つ抗酸化作用を利用した治療方法です。
点滴で高濃度のビタミンCを投与することで、腫瘍細胞の増殖を抑える効果が期待されています。
何より副作用が少なく、継続しやすいのも大きなメリットです。
これらの治療を続けるうちに性格が穏やかになり、あれほど頑固だった食事もちゃんと食べるようになりました。
「前より素直になって、いろんなごはんを受け入れてくれるようになった」
飼い主さんが驚きと喜びを口にするほど、まるで心まで変わったように見えたそうなんです!
病気をきっかけに、この子自身が何かを悟ったかのようでした。

一般的な口腔内骨肉腫の余命
犬の口腔内骨肉腫は進行が早く、平均的な余命は数週間から数か月といわれます。
外科手術で完全に取り切れることも少ないし、再発や悪化が避けられないこともあります。
一般的な余命は、以下のように言われています。
外科治療なし;数週間~数か月
外科のみ;3~6か月
外科+放射線;6~12か月
完全切除;1年以上
6か月を越えて元気に過ごす
しかしこの子は一般的な予想を超えて、毎日を元気に過ごしています。
もちろん、腫瘍の性質や体質も影響しているかもしれません。
けれど少なくとも高濃度ビタミンC療法が進行を抑え、生活の質を支えていることは確かなように思いま。
そしてなにより病気をきっかけに、なぜか「食べる楽しみ」を知ったことです。
しかも「わがままな性格」も変わり、家族の皆と接する姿勢が変わった・・・・
これは飼い主さんにとって、とっても喜ばしいことでした。
生活の質を守る工夫
腫瘍を完全に取り除けなくても、痛みを和らげ毎日を快適にする治療があります。
- 鎮痛剤や消炎剤で痛みをコントロール
- 栄養をつけるために食事の工夫をする
- 出血や感染に対して抗生剤や止血の処置
- 飼い主さんと安心して過ごせる楽しい時間をつくる
「余命を延ばすこと」だけでなく「その子らしい日々を過ごすこと」が、治療の大切な目的です。
何よりも「大好きな家族と安心して過ごす時間」が、この子の生命力のパワーになっています。
治療を選ぶときに大切なこと
腫瘍の治療方法には「正解はひとつ」では無い、そのように思うのです。
- 延命を第一に考えるのか
- 生活の質を大切にするのか
- 手術や放射線に踏み切るのか
それぞれのご家庭で大切にしていることや、その子の性格、体力によっても選択肢は変わってきます。
当院では、飼い主さんと一緒に「その子らしい過ごし方」を考えることを大切にしています。

まとめ
口腔内骨肉腫は、決して簡単な病気ではありません。
多くの場合、その余命は数か月単位で語られます。
けれど、この子が見せてくれたのは「病気の中でも変われるものがある」という姿でした。
わがままで食に興味を示さなかったのに、食べる楽しみを知り、そして半年以上も家族と過ごしている・・・・
それは家族の皆様の愛情がもたらした奇跡だと思っています。
そして「一日一日を大切に過ごすこと」こそが、病気と向き合う上で一番大切なものとも言えます。